No.2273,772
もう行けるお店がない
高齢者の方が寂しそうにつぶやいていました。

昨今の事業のDX推進で
飲食店がQRコードの注文になったり
便利な反面、お年を召した方には
優しくないことになっています。
~*~*~*~*~*~*~*~*
ITに詳しくない中小企業に寄り添う
竹内美紀です。
2つの講座とノート1枚で
欲しい結果を手に入れる方法を
お伝えしています
当社の解説(7分)↓
~*~*~*~*~*~*~*~*
キャッシュレス決済やQRコードでの注文。
確かに、これらは私たちビジネス側にとって、
効率化やコスト削減、
データ収集といった多大なメリットを
もたらしてくれます。
スマートフォンの普及率が上がり、
デジタルネイティブ世代が
顧客の中心となりつつある今、
DX(デジタルトランスフォーメーション)推進は
企業にとって避けては通れない道でしょう。
しかし、その「便利さ」「効率性」の波が、
すべての人にとって優しいものであるとは
限りません。
特に、デジタルデバイスの操作に
不慣れな方々にとって、
それは時に利用をためらわせる壁となり、
冒頭のつぶやきのように
「置いてけぼり」感を
生んでしまう可能性すらあります。
経営者の皆様は、
DXを推進される中で、
このような声に耳を傾けていらっしゃるでしょうか?
DX推進のその先に失われるもの
デジタル化による効率化は、
人件費の削減やオペレーションの迅速化に
貢献します。
これは競争が激化する現代において、
非常に重要な要素です。
しかし、その過程で、
これまで当たり前だった
「人による温かい対応」
「ちょっとした気遣い」
「対面での安心感」
といった、アナログな部分が失われていないか、
立ち止まって考える必要があります。
飲食店での
「すみません、注文いいですか?」
と店員さんを呼ぶ行為。
アパレル店で店員さんとおしゃべりしながら服を
選ぶ時間。
地域の商店で
「いつものね」
と顔なじみの店主と交わす会話。
これらは効率とは
真逆にあるように見えて、
実は顧客体験の質を高め、
顧客のロイヤリティを醸成し、
地域社会との繋がりを深める、
かけがえのない要素です。
これらのアナログな価値を、
効率化の名のもとに
すべて排除してしまうことは、
長い目で見ると大きな損失に繋がりかねません。
「もう行けるお店がない」
と感じるお客様が増える
ということは、特定の顧客層を失うだけでなく、
「人に優しくない店」というイメージが広がり、
新規顧客獲得にも悪影響を及ぼすリスクがあるのです。
アナログとデジタルの「心地よい」融合を目指す
では、どうすればよいのでしょうか?
DXによる利便性と効率性を追求しながら、
すべてのお客様が疎外感を感じることなく、
むしろ「このお店は自分に優しい」と
感じていただけるような
サービスを提供するには?
その答えは、
「アナログとデジタルの心地よい融合」
にあると考えます。
どちらか一方を選ぶのではなく、
それぞれの利点を活かし、
顧客にとって選択肢となるような
ハイブリッドな仕組みを構築するのです。
融合の具体的な例
- 飲食店:
- QRコード注文を導入しつつ、紙のメニューも引き続き設置する。
- 操作に困っているお客様向けに、呼び出しボタンや「声かけ歓迎」の意思表示をする。
- ピーク時はデジタルで効率化を図り、比較的余裕のある時間帯はスタッフによる丁寧な説明や雑談を取り入れる。
- 小売店:
- オンラインストアを充実させつつ、実店舗ではスタッフによる細やかな接客やコーディネート提案を強化する。
- セルフレジと有人のレジを併設する。
- デジタルクーポンやポイントシステムと並行して、昔ながらのスタンプカードも用意する。
- サービス業:
- ウェブサイトからのオンライン予約システムを導入しつつ、電話予約も受け付ける。
- チャットボットによる自動応答と、オペレーターによる有人対応を組み合わせる。
- デジタル会員証と物理的な会員証を用意する。
重要なのは、
「デジタル化しました、以上」
で終わらせないことです。
デジタルツールはあくまで手段であり、
目的はお客様に快適にサービスを
利用していただき、
満足度を高めることにあります。
デジタル化を進める際に、
必ず「この変更によって、これまでご利用いただいていたお客様の中に困る人はいないか?」
「どうすれば、デジタルに不慣れな方でも安心して利用できるか?」
という視点を持つことです。
スタッフの方々への教育も不可欠です。
単にデジタルツールの操作方法を
教えるだけでなく、
「デジタルが苦手なお客様にはどのように声かけをするか」
「どのようなサポートが必要か」
といった、アナログな接客スキルの重要性を
再認識してもらうことが、
融合経営の鍵となります。
顧客層の多様性を理解し、すべての声に耳を傾ける
経営者の皆さん。
自社の顧客層の多様性を
改めて分析してみてください。
デジタルネイティブ世代、
働き盛りの世代、
そして今回話題になった高齢者の方々。
それぞれの世代が持つ
デジタルへの習熟度や、
サービスに求めるものは異なります。
すべての顧客層に寄り添うためには、
一部の層にとっての
「便利さ」
だけを追求するのではなく、
幅広い層が安心して利用できるような
配慮が必要です。
そして、最も大切なのは、
現場のスタッフの声、
そしてお客様から直接いただく
「生の声」に真摯に耳を傾けることです。
「もう行けるお店がない」
という声は、決して無視してはならない
ビジネス上のサインです。
それは、デジタル化の波に乗り遅れた
一部の人の問題ではなく、
企業が顧客全体に対する配慮を
怠っている可能性を示唆しているからです。
人に優しいDXが、真の競争力となる
DX推進は、
ビジネスの効率化・最適化に
不可欠な現代の潮流です。
しかし、その推進が
「人に優しいサービス」という、
日本がこれまで培ってきた強みを
損なうものであってはなりません。
アナログとデジタルのそれぞれの良さを
理解し、それらを戦略的に融合させること。
すべての顧客層に選択肢と
安心感を提供すること。
それは、単なる思いやりではなく、
顧客満足度を高め、
LTV(顧客生涯価値)を向上させ、
結果として企業の持続的な成長に繋がる、
真の競争力となり得ます。
効率と人間味。
この二項対立で捉えるのではなく、
いかに両立させるか、
いかに相乗効果を生み出すか。
「もう行けるお店がない」
と寂しそうにつぶやく方が一人でも減るように、
経営者の皆様と共に、人に優しいデジタル社会、
そしてアナログの温かさも共存する
心地よいサービス提供のあり方を
探求していければ幸いです。
さてさて。
高齢者の方々。
スマホを練習するのも
1つの選択ですよ。
想いが伝わり、成果があがる
そんな仕組みを作るお手伝いをさせてください。
~*~*~*~*~*~*~*~*
個別相談は下記フォームからもどうぞ。
※誠意のない営業に対してはお返事しないこともあるかもしれません。
========================





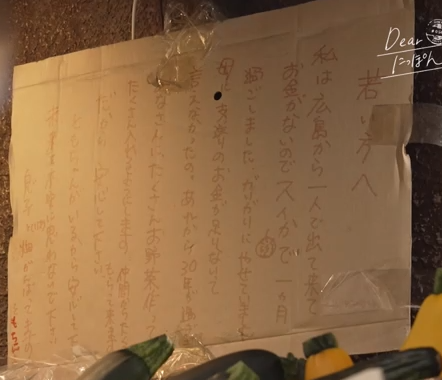


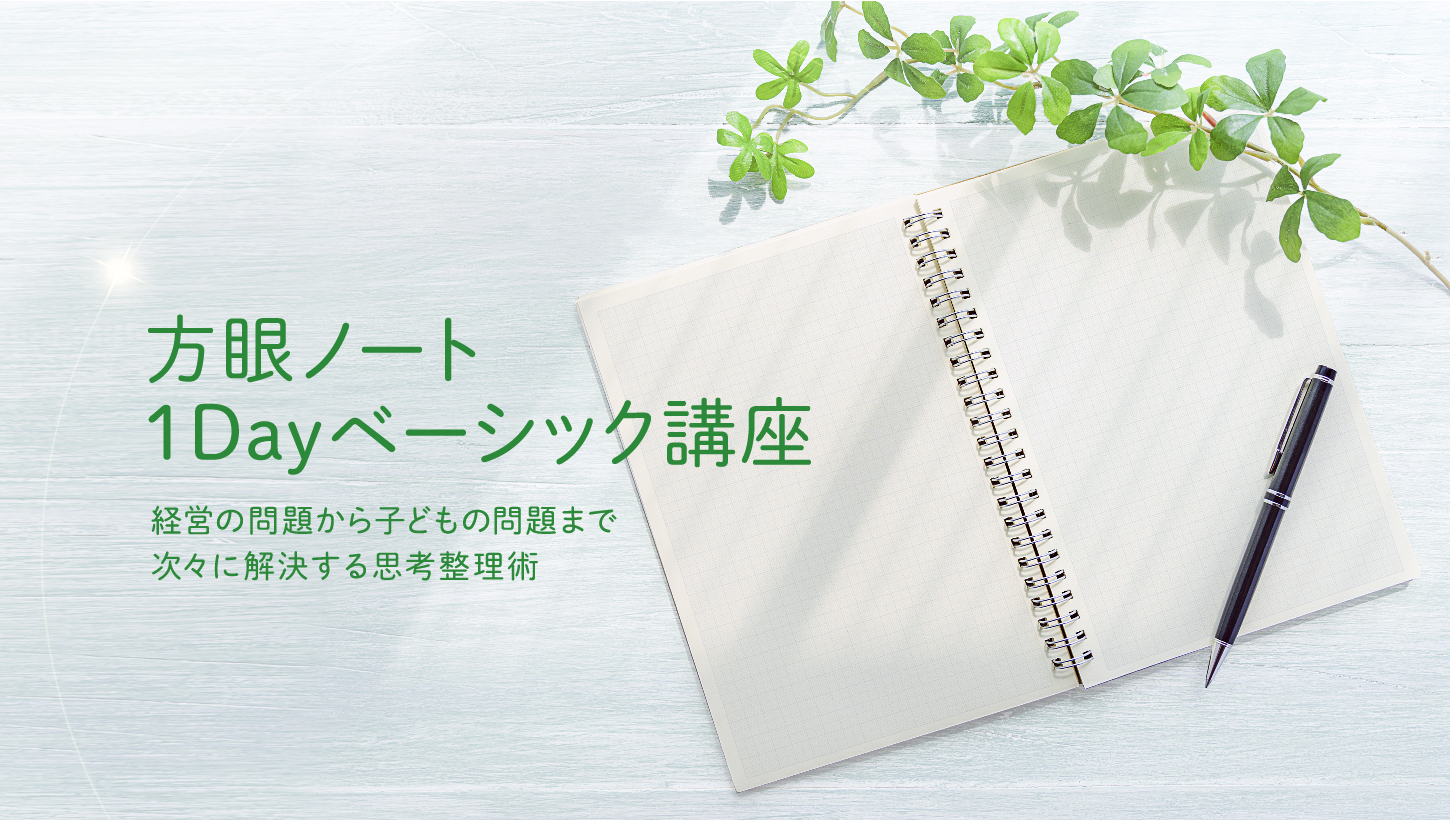

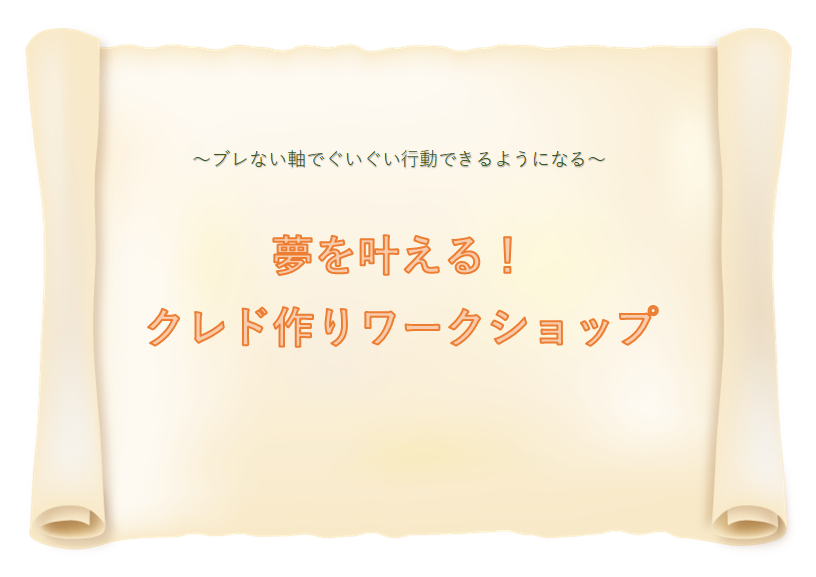
この記事へのコメントはありません。